物流革命の主役!3PL企業が変える日本のサプライチェーンの未来とは

現代の物流業界で注目される3PL企業について、基本的な概念から導入メリット、市場動向まで詳しく解説します。倉庫業との違いや大手企業の取り組み事例も紹介し、3PL導入を検討している企業が知っておくべき情報を網羅的にお届けします。
目次
- ■3PL企業の基本概念と役割
- ■アセット型とノンアセット型の特徴比較
- ■従来の倉庫業との明確な違い
- ■3PL導入で得られる3つの主要メリット
- ■急成長する3PL市場の現状
- ■業界をリードする大手3PL企業の戦略
- ■3PL導入成功のポイントと今後の展望
■3PL企業の基本概念と役割
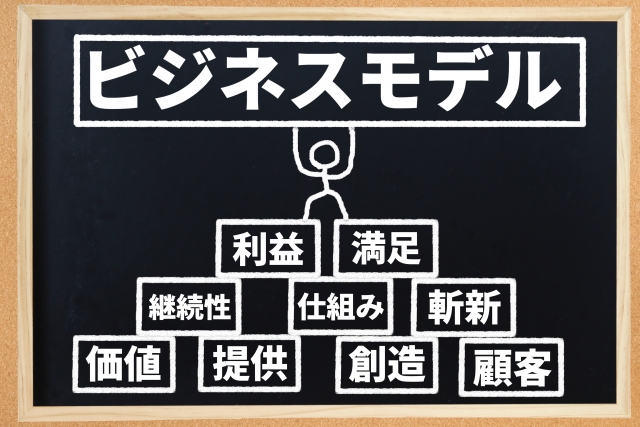
3PLとは「サードパーティ・ロジスティクス(Third Party-Logistics)」の略称で、荷主企業に代わって第三者が物流システム全体の企画・設計・運営を包括的に請け負う事業形態を指します。
3PL企業は単なる物流代行業者ではありません。効率的な物流システムの提案から実際の運営まで、物流業務の全工程を戦略的に管理する専門企業です。
国土交通省も3PLの普及を積極的に推進しており、その理由は明確です。3PLの普及により実現される物流効率化は、コスト削減だけでなく、CO2排出量の削減による環境負荷軽減、さらには地域経済の活性化にも大きく貢献するためです。
物流業界における当事者の関係性を整理すると、ファーストパーティーは「メーカーなど供給企業」、セカンドパーティーは「問屋や小売事業者」、そして3PL企業が「第三者的立場の物流専門企業」という位置づけになります。
■アセット型とノンアセット型の特徴比較
3PL企業は保有資産の有無により「アセット型」と「ノンアセット型」の2タイプに分類されます。
| 項目 | アセット型 | ノンアセット型 |
| 保有設備 | 倉庫・車両・配送センターを自社保有 | 設備を持たずコンサル機能に特化 |
| 強み | 蓄積されたノウハウを活用可能 | 中立的な立場での最適提案 |
| 課題 | 自社資産活用が優先されがち | 実行力は外部パートナー次第 |
○アセット型3PL企業の特徴
アセット型企業は、倉庫や運送車両、配送センターなどの物流インフラを自社で保有しています。長年の運営により蓄積されたノウハウを活用できる点が最大の強みです。
ただし、自社保有資産の活用を優先する傾向があるため、必ずしも荷主企業にとって最適な提案とならない場合もあります。
○ノンアセット型3PL企業の特徴
ノンアセット型企業は物流設備を持たず、物流戦略の立案と最適な外部パートナーとのマッチングを専門としています。
利害関係のない第三者として、純粋に荷主企業の利益を最大化する提案ができることが特徴です。中小企業にとって、限られた経営リソースをコア業務に集中させる戦略として特に有効です。
■従来の倉庫業との明確な違い

倉庫業と3PL企業の役割には根本的な違いがあります。倉庫業は「荷物の保管」が主業務ですが、3PL企業は「物流全体の最適化」を担います。
倉庫業務は3PLが管理する物流機能の一部に過ぎません。3PL企業が管理する業務範囲には、配送・輸送、保管・荷役、梱包・包装、ラベル付けなどの流通加工、情報システム管理など、製品が消費者に届くまでの全工程が含まれます。
○入庫時の主要業務
- 荷卸しと入庫伝票との照合・確認
- 商品内容の詳細検品
- 保管場所別の仕分け作業
○出庫時の主要業務
- 出荷商品の品出し(ピッキング)
- 出荷前の最終検品
- 商品保護のための適切な梱包
- 出荷伝票との照合確認
このように倉庫業は物流プロセスの一部分を担う役割ですが、3PL企業はこれら全体を統合管理し、最適化を図る包括的なサービスを提供します。
■3PL導入で得られる3つの主要メリット
3PL導入により企業が得られる具体的なメリットを3つの観点から解説します。
○納品リードタイムの短縮とサービス品質向上
3PL企業は物流業務の専門集団として、長年蓄積されたノウハウと最新の情報システムを駆使した効率的な運用を実現します。
その結果、納品リードタイムの大幅短縮が可能になり、多頻度小口配送などの高度な顧客ニーズにも柔軟に対応できます。物流品質の向上は直接的に顧客満足度の向上につながります。
○物流コストの大幅削減
自社物流では、物量に関係なく倉庫費用や人件費が固定費として発生します。加えて、設備投資や適切な管理体制の構築にも相当なコストがかかります。
3PL企業への委託により物流コストが可視化され、運用の見直しを通じて大幅なコスト削減が期待できます。
○人的リソースのコア業務集中による生産性向上
物流業務には専門スキルを持つ人材の配置が不可欠ですが、限られた人材を物流に割り当てることで、商品企画や店舗開発などのコア業務の人材不足が生じる可能性があります。
3PL委託により、貴重な人材をより付加価値の高い業務に集中できるため、全体的な生産性向上が実現します。
■急成長する3PL市場の現状

近年、高速道路インターチェンジ周辺での大規模物流施設建設ラッシュの背景には、3PL市場の急速な拡大があります。
3PL市場規模は中長期的な成長トレンドを維持しており、数年前の時点で既に約3.3兆円に達しています。この成長の主要因として以下が挙げられます。
- EC市場拡大に伴う多頻度小口輸送需要の増加
- 深刻化するトラックドライバーの人手不足
- 物流品質維持・向上への企業ニーズの高まり
特に「物流業界の2024年問題」として議論される働き方改革関連の課題への対策として、3PL企業への関心がさらに高まっています。
■業界をリードする大手3PL企業の戦略
主要3PL企業の特徴的な取り組みを紹介します。
○日本通運
総合物流インフラの活用 日本通運では、倉庫管理システムや輸配送管理システムを自社開発し、荷主企業の業態に合わせたカスタマイズを実現しています。
国内外の豊富な物流インフラを活用し、陸路・海路・空路すべての輸送手段に対応可能です。受発注処理から決済代行、通関業務まで、幅広い物流機能を一貫して提供し、ノンアセット型サービスも含めた柔軟なサービス展開が特徴です。
○日立物流
スマートロジスティクスの先駆者 1980年代から3PL事業を手掛けるパイオニア企業として、国内外に760のグローバル拠点を展開しています。
豊富な経験に基づくデータ分析力と、「スマートロジスティクスコンフィギュレータ」を活用したシミュレーション提案が強みです。無人搬送車導入などの最新技術も積極的に推進し、スマートロジスティクス分野をリードしています。
○鈴与
業種特化型オーダーメイドサービス 日用雑貨、食品、ファインワイン、医療機器、自動車関連、小売・ECなど、多様な業種に特化した3PLサービスを展開しています。
小売店向けには物流センター運営と共同配送による効率化を、ファインワインには専用定温倉庫での保管サービスを提供し、150社以上との取引実績を築いています。
■3PL導入成功のポイントと今後の展望

国土交通省は3PL普及による地球温暖化対策、地域雇用創出効果を重視し、人材育成推進事業やガイドライン策定、税制特例措置により総合的に3PL事業を支援しています。
3PL企業の活用により、自社での物流管理負担が大幅に軽減されます。物流システムの提案から構築まで一括対応により、手間をかけることなく最適な物流体制が実現できます。
ただし、3PL導入にあたっては慎重な検討が必要です。過度なコスト削減期待は期待した効果を得られない結果につながる可能性があり、業態による向き・不向きも存在します。
成功の鍵は、現状の物流品質を維持しつつ、どの程度のコスト削減が実現可能かを正確に把握することです。導入前の詳細な分析と慎重な検討を重ねることで、3PL導入の真価を最大限に引き出すことができるでしょう。
↓↓お問い合わせはこちら↓↓









