物流アウトソーシングとは?メリット・注意点・成功のコツまでまるっと解説!

目次
◾️物流アウトソーシングとは?
◾️なぜ今、アウトソーシングが注目されているのか?
◾️どんな業務をアウトソーシングできるの?
◾️アウトソーシングのメリットと注意点
◾️どんな企業に向いているの?
◾️導入するとどう変わる?業務のビフォーアフターで解説
◾️物流アウトソーシングを成功させるために大事なこと
◾️神谷商店の物流アウトソーシングでできること・強み
◾️まとめ:物流アウトソーシングはビジネス成長の土台に
↓↓お問い合わせはこちら↓↓
◾️物流アウトソーシングとは?
物流アウトソーシングとは、商品の保管・梱包・出荷などの物流業務を、自社ではなく外部の専門業者に委託することをいいます。
ネットショップを運営している方やメーカー・小売業などでは、注文が増えてくると、出荷作業や在庫管理などに時間がとられ、本業に手が回らなくなることがあります。
そんなときに頼りになるのが「物流のプロ」にまかせるアウトソーシングです。
自社で倉庫を構えたり、人員を採用・教育したりする必要がなくなるため、コストを抑えて業務の安定化ができるのが大きな魅力です。
♦︎外注できる物流業務って、どんな内容?
物流アウトソーシングと一言で言っても、委託できる内容は多岐にわたります。以下のように分類できます。
| 項目 | 内容 | 委託できる業務例 |
| 保管 | 商品を安全に預かる | 常温・冷蔵・棚・パレット管理など |
| 入出庫 | 商品の受け入れ・出荷準備 | 入庫検品、ロケーション管理、ピッキングなど |
| 梱包・発送 | 注文に応じて出荷 | 箱詰め、緩衝材、伝票発行、配送手配 |
| 付帯作業 | プラスαの対応 | ギフト対応、チラシ封入、返品受付など |
| システム連携 | ECサイトとのデータ同期 | WMS・API連携・在庫自動更新など |
これらを一括して引き受けてくれるのが物流アウトソーシングの強みです。
◾️なぜ今、アウトソーシングが注目されているのか?
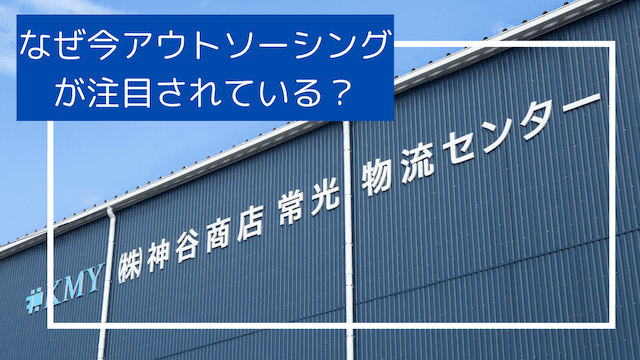
ここ数年、「物流アウトソーシング」に注目が集まっているのには、いくつかの背景があります。
単に作業を外に出すというだけでなく、時代の変化に合わせた合理的な経営判断として選ばれるケースが増えているのです。
1. EC市場の拡大で出荷が追いつかない
コロナ禍をきっかけに、ネットショッピングの利用は急拡大しました。
小さなネットショップでも注文が爆発的に増えた一方で、「人手が足りない」「スペースが足りない」という課題を抱える事業者が増えています。
特にセールやキャンペーン時期には、普段の3倍、5倍という出荷件数になることも。
そんな中で「自社対応」に限界を感じ、アウトソーシングに切り替える動きが進んでいます。
2. 人材確保の難しさと人件費の高騰
物流の現場では、ピッキングや梱包などに人の手が必要です。
しかし、労働人口の減少や人件費の上昇により、「人を採用できない・定着しない」という悩みを抱える企業が少なくありません。
外部の専門業者に任せれば、教育やシフト調整などの負担が減り、安定した稼働を維持することができます。
3. 変化の早いビジネスに柔軟に対応したい
ネットショップでは、扱う商品や販売チャネルがどんどん変化します。
「新商品を出したい」「販促キャンペーンでチラシを入れたい」「急に配送キャリアを変えたい」など、柔軟な対応が必要です。
そうした時に、設備や人員の固定化を避けられるアウトソーシングは、変化に強く、スピーディーに対応できる手段として活用されています。
♦︎アウトソーシングが選ばれる理由まとめ(表)
| 理由 | 内容 | 経営上のメリット |
| EC需要の拡大 | 出荷件数が急増し、手作業が限界に | 業務の効率化・安定稼働 |
| 人材不足とコスト高 | 採用難、人件費の上昇 | 固定費削減・労務負担の軽減 |
| 市場変化への対応 | キャンペーンや新商品の頻発 | フレキシブルな運用が可能に |

◾️どんな業務をアウトソーシングできるの?

「物流アウトソーシング」と聞くと、「全部任せるのは不安…」と思う方もいるかもしれません。
でも実際は、一部の作業だけ任せることも、すべてを一括でおまかせすることも可能です。
ここでは、物流業務の中でアウトソーシングできる代表的な作業内容を、わかりやすくご紹介します。
1. 入庫(荷受け・検品)
まずは、メーカーや仕入れ先から届いた商品の受け取り。
段ボールを開けて、数量や状態を確認する検品作業も含まれます。
この工程を任せることで、自社での荷受け作業が不要になり、スペースや時間に余裕が生まれます。
2. 保管・在庫管理
倉庫の一角を借りるような形で、在庫を外部に預けることができます。
保管するだけでなく、WMS(倉庫管理システム)を使ってリアルタイムで在庫数の確認・調整も可能です。
これにより、「商品がどこにあるのかわからない」「在庫ズレが起きた」というミスも減らせます。
3. ピッキング(商品取り出し)
注文が入ったら、その内容に合わせて正しい商品を棚から取り出す「ピッキング」。
バーコードやハンディ端末を使った正確な作業が行われ、ヒューマンエラーの削減につながります。
4. 梱包・同梱作業
商品の大きさに合わせた箱や袋を選び、丁寧に梱包する作業もアウトソーシング可能。
さらに、チラシ・クーポン・ノベルティなどの同梱にも対応している業者なら、販促活動までサポートしてもらえます。
5. 出荷・配送手配
伝票の発行、宅配便業者との連携など、発送までの作業をすべて任せられるのも大きなポイント。
出荷作業の負担を丸ごと削減できますし、当日出荷・翌日配達などスピード重視の運用にも対応できます。
6. 返品対応・再商品化
万が一、返品が発生した場合もアウトソーシング可能。
返品された商品を倉庫が受け取り、状態チェック→再販可否の判断→在庫への反映まで行ってくれます。
これにより、自社での返品処理が不要になり、業務の効率化に直結します。
♦︎よくアウトソーシングされる業務まとめ
| 業務内容 | 説明 | アウトソーシングの効果 |
| 入庫・検品 | 商品の数量・状態をチェックして登録 | 作業負担の軽減・ミス削減 |
| 保管・在庫管理 | 商品を預かり、WMSで数量を管理 | スペースの有効活用・リアルタイムで在庫確認 |
| ピッキング | 注文に応じて商品を正確に取り出す | 出荷ミスの防止 |
| 梱包・同梱 | 商品に合った梱包+チラシや特典封入 | 丁寧な配送・ブランド力アップ |
| 出荷・配送手配 | 宅配便との連携、送り状発行、発送 | 即日出荷対応・手間削減 |
| 返品対応 | 商品の受け取り〜再販判断まで | 業務時間の短縮・在庫ロス削減 |
アウトソーシングできる範囲は思っている以上に広く、目的や状況に合わせて“必要なところだけ”頼むことも可能です。
まずは、自社で手間がかかっている工程から見直してみると、最初の一歩が踏み出しやすくなります。
◾️アウトソーシングのメリットと注意点
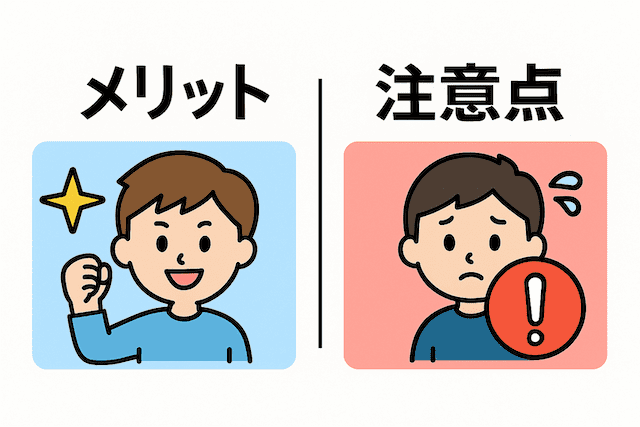
物流アウトソーシングを導入することで、企業の業務効率やコスト面に大きなメリットが生まれます。ただし、メリットばかりに目を向けていると「こんなはずじゃなかった…」という結果になることも。
ここでは、物流アウトソーシングの代表的なメリットと、あらかじめ知っておきたい注意点をまとめました。
♦︎アウトソーシングの主なメリット
1. 業務の負担が軽くなる
一番大きな効果は、日々の出荷・在庫管理といった作業から解放されること。
ピッキング・梱包・発送などの手間をプロに任せられるので、スタッフは企画や営業、カスタマーサポートなど「売上につながる仕事」に集中できます。
2. 専門性のある作業で品質が安定
物流会社は「出荷のプロ」。
バーコードによる管理や、仕分け・梱包のノウハウが豊富なので、出荷ミスや納期遅延が大きく減少します。
また、商品の扱いにも慣れており、梱包の美しさや丁寧さも安心ポイントです。
3. コストの平準化と削減
倉庫スペース・人件費・梱包資材など、自社運用だと毎月かかる固定費を、物流会社に任せることで「使った分だけ」の従量課金に変えられます。
その結果、閑散期のコストを抑えられ、繁忙期には対応力が上がるという柔軟な運用が可能になります。
4. スピード対応とキャパシティ拡大
セールやキャンペーンで急に注文が増えても、物流センターの人員・設備を活かして即日対応が可能。
「発送が追いつかない」というトラブルを防ぎ、機会損失を減らすことができます。
♦︎一方、気をつけたいポイント
1. 自社での柔軟な調整が難しくなることも
アウトソーシングでは、すべての作業を他社に依頼するため、「急に手書きメッセージを入れたい」「ギフト包装を変えたい」などの細かな変更はすぐにできないこともあります。
事前にどこまで対応してもらえるか、ルールをしっかり確認することが重要です。
2. 情報共有・連携ミスのリスク
注文情報や商品マスタの更新など、自社と物流会社間の連携がうまくいかないと、出荷ミスや在庫のズレが発生することも。
「どのタイミングで、どんな情報を共有するのか」「誰が責任を持つのか」といった運用ルールの整備が欠かせません。
3. 最低利用量や契約縛りに注意
一部の物流サービスでは、「月◯件以上の出荷が必要」「最低6ヶ月契約」などの条件が設定されていることがあります。
始める前にコスト試算と契約条件のチェックは必須です。
♦︎メリットと注意点まとめ
| 項目 | 内容 | ポイント |
| 作業負担軽減 | 出荷・在庫・梱包などを任せられる | 社内の時間を本業に使える |
| 品質安定 | ミスや遅延が減り、梱包も丁寧 | 顧客満足と信頼アップ |
| コスト最適化 | 固定費から変動費へ | ムダなく運用できる |
| キャパ対応 | 繁忙期の増加にも即対応 | 機会損失の防止 |
| 柔軟性に限界あり | 突発的な変更には弱い | 契約内容のすり合わせが大切 |
| 情報連携が重要 | データ共有ミスに注意 | 運用ルールの整備がカギ |
まとめ
物流アウトソーシングは、コスト・作業時間・品質のすべてを改善できる心強い選択肢です。
でも、すべてを任せきりにするのではなく、「自社に合った業務だけを委託する」「連携体制をきちんと整える」ことが成功のカギ。
メリットと注意点をしっかり理解したうえで、自社の課題にフィットする形で活用するのが理想的です。
◾️どんな企業に向いているの?

物流アウトソーシングは便利な仕組みですが、すべての企業にとってベストな選択肢というわけではありません。
「どんな企業に向いているのか?」「どんな状態になったら検討すべきか?」――このような悩みにお答えします。
ここでは、物流アウトソーシングがとくに効果を発揮する企業の特徴を具体的にご紹介します。
1. 注文が増えて現場が回らなくなってきた企業
ECや小売ビジネスを展開している中で、月の注文数が300件〜500件を超えると、自社対応では限界を感じることが多くなります。
とくにキャンペーンやセールの時期は出荷業務がパンクしやすく、「残業で乗り切る」状態が続いているなら危険信号です。
物流アウトソーシングを活用すれば、繁忙期でも安定した出荷体制が維持できるため、作業の山を乗り越えるための一時対応ではなく、中長期的な安定運用が可能になります。
2. 少人数や兼任で業務を回している企業
担当者が「出荷も在庫もお客様対応も全部やっている」という状態では、どうしても業務が回りきらなくなります。
とくに社内に物流専任の担当者がいない場合は、少しでも出荷件数が増えると他の業務がストップしてしまうことも。
物流アウトソーシングを導入することで、限られた人数でも効率よく運営ができるようになり、結果的に売上アップや業務の質向上にもつながります。
3. 商品数やSKUが多い企業
アパレルや雑貨など、サイズ違いや色違いなどバリエーションの多い商品を扱っている企業は、自社倉庫だとピッキングミスが増えがちです。
在庫管理も複雑になり、「あるはずの商品が見つからない」「誤出荷でクレームが入る」といったトラブルも発生します。
WMS(倉庫管理システム)やバーコードスキャンを使ったプロの現場に任せることで、ミスが激減し、在庫のズレも解消されます。
4. 今後の成長を見越している企業
「今はまだ注文が少ないけど、半年後には売上を倍にしたい」というような、成長志向のある企業にもおすすめです。
最初からアウトソーシングの仕組みを整えておけば、売上が伸びても無理なく対応できる体制が整い、安定した成長が可能になります。
社内での人員拡充や倉庫移転の必要もなく、スモールスタートからスムーズにスケールアップできるのが物流アウトソーシングの大きな魅力です。
♦︎どんな企業に向いている?チェック表
| 状況 | 企業の特徴 | 向いている理由 |
| 出荷件数が増えてきた | 月300件以上の出荷がある | 社内の作業負担を軽減できる |
| 少人数で運営している | スタッフ1〜2名で兼任している | 出荷業務を切り離して効率化できる |
| SKUが多い | 色・サイズ違いなどのバリエーションが多い | ピッキングミス・在庫ズレを防げる |
| 成長を目指している | 注文数・商品数が増える予定がある | 拡張性のある体制を先に構築できる |
| 出荷作業が煩雑 | 梱包・伝票・資材手配が手間になっている | 外注化することでコア業務に集中できる |
まとめ
物流アウトソーシングが向いている企業には、「忙しすぎる」「人が足りない」「今後伸ばしたい」という共通点があります。
逆に言えば、まだ1日数件の注文で、社内で余裕を持って対応できている企業には、必ずしも必要とは限りません。
重要なのは、「今の状態」と「これからの目標」を照らし合わせて判断することです。
将来の成長を妨げる要因にならないよう、早めに体制を見直しておくことが、持続的なビジネス成功のカギになるでしょう。
◾️導入するとどう変わる?業務のビフォーアフターで解説

物流アウトソーシングを導入すると、「ただ楽になる」だけではなく、現場の働き方そのものが大きく変化します。ここでは、導入前と導入後で、具体的にどんな変化があるのかをわかりやすく紹介します。
出荷作業の流れがスムーズになる
これまで自社内で対応していた場合、出荷のたびに在庫確認→ピッキング→梱包→伝票作成→集荷依頼という工程を、限られた人手でこなさなければなりませんでした。忙しい時期には、残業や発送遅れも発生していたかもしれません。
アウトソーシング導入後は、この一連の作業を物流会社が代行。しかも、システムで注文と連携しているため、人の手を介さず出荷作業が始まる仕組みが整います。これにより、作業スピードは格段にアップ。スタッフは出荷の段取りから解放されます。
担当スタッフの役割が変わる
導入前は、担当者が商品の確認から梱包、送り状の発行、クレーム対応までを1人で対応していたケースもあるでしょう。業務が多岐にわたるため、常に作業に追われ、「本当に必要な業務に集中できない」状況に陥っていたはずです。
導入後は、物流業務が自動化・外注化されることで、担当者は顧客対応や商品ページの改善、販促企画など“売上を伸ばすための仕事”にシフトできます。
ミスやトラブルが起きにくくなる
手作業中心だった頃には、出荷ミスや送り状の貼り間違い、二重発送など、小さなトラブルが積み重なりやすい状況にありました。
物流会社の現場ではWMS(倉庫管理システム)やバーコードによる管理体制が整っており、作業の正確性が飛躍的に向上します。その結果、クレーム件数が減り、レビュー評価が安定するといった変化も見られるようになります。
♦︎業務フローのビフォーアフターまとめ
| 項目 | アウトソーシング前 | アウトソーシング後 |
| 出荷作業 | 毎回スタッフが手動で対応 | 自動連携+物流会社が一括処理 |
| 担当者の業務 | 梱包・伝票・集荷手配などで毎日バタバタ | 顧客対応や企画などに集中できる |
| 発送ミス | 手作業中心で起きやすい | WMSやバーコードでミス激減 |
| 時間の使い方 | 作業中心、戦略業務に手が回らない | 売上に直結する業務に注力可能 |
| 顧客満足度 | 発送遅れやミスで評価に影響 | 早く正確に届き、評価も安定 |
まとめ:仕事の“質”が変わる
物流アウトソーシングの導入によって、単なる業務の外注ではなく、社内の業務の質・働き方・顧客対応のレベルそのものがアップデートされます。
「手間が減る」だけではなく、「本来やるべき仕事に集中できる環境が整う」
これが、導入後の本当の変化です。
◾️物流アウトソーシングを成功させるために大事なこと
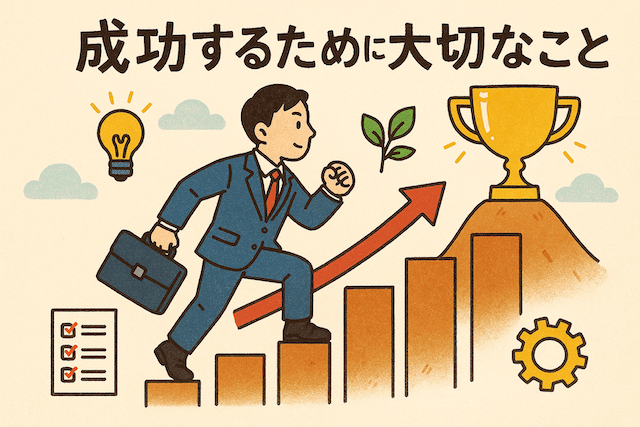
物流アウトソーシングはとても便利な仕組みですが、「任せたけど思ったようにいかなかった…」というケースもゼロではありません。
うまく活用するには、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが必要です。
ここでは、物流アウトソーシングを成功させるための実践的なコツをご紹介します。
1. 「丸投げ」ではなく「連携」する姿勢が大切
アウトソーシングというと「すべて任せられる」というイメージがありますが、最初から完全にお任せするとうまくいかないことも。
自社の商品や顧客層を一番理解しているのは、自社の担当者です。
たとえば:
- 壊れやすい商品はどんな緩衝材が最適か?
- 人気商品はどの順番で出荷するべきか?
こうした情報を物流パートナーとしっかり共有し、一緒に仕組みを作っていく意識が重要です。
2. 情報の整理とマニュアル整備をしておく
物流現場では、「どう梱包するか」「どのラベルを貼るか」「同梱物は何か」など細かい判断が日常的に発生します。
これを毎回メールや口頭で伝えるのではなく、あらかじめルール化・マニュアル化しておくことで、作業のばらつきやミスを防ぐことができます。
おすすめは以下のような内容を文書にしておくこと:
- 商品別の梱包方法
- 出荷ルール(納期や締切時間など)
- 同梱物や販促物のパターン
- ラッピング・のし対応の基準
「誰が見てもわかる」状態にしておけば、新しいスタッフでもすぐに現場対応が可能になります。
3. トラブル対応のフローを共有しておく
物流現場では、破損・返品・発送遅延など、どうしてもトラブルは起こり得ます。
重要なのは、「トラブルが起きたとき、どう対応するか」が決まっているかどうかです。
事前に以下のようなフローを決めて共有しておきましょう:
- 誤出荷が起きた場合の対応
- 返品された商品の扱い方(再販可/廃棄)
- 発送遅延が発生したときの連絡体制
こうした「事前の合意」があるだけで、トラブル時の対応スピードやお客様対応の質が大きく変わります。
4. 定期的な振り返りと改善の時間を設ける
一度委託を始めたらそのまま…というのではなく、定期的なレビューやミーティングを行うことが成功のカギです。
たとえば:
- 月に一度の出荷状況レビュー
- クレーム件数や出荷ミスの共有
- 改善提案や新しい取り組みの相談
物流パートナーを「ただの外注先」と捉えるのではなく、自社と一緒に成長するチームメンバーとして扱うことが、長くうまく続けるコツです。
♦︎成功のためのチェックリスト
| ポイント | 内容の要点 | 成功につながる理由 |
| 丸投げしない姿勢 | 梱包・出荷ルールは一緒に考える | 現場との認識ずれを防げる |
| 情報を整理してルール化 | マニュアル・手順書を用意する | ミスの減少・教育コストの削減 |
| トラブル時の対応フローを明確にしておく | 誤出荷・返品時の対応基準を事前に決める | 顧客対応のスピード・品質が上がる |
| 定期的に振り返りをする | 出荷実績やクレーム内容を共有・改善する | パートナーとの関係が長期的に良好に保てる |
物流アウトソーシングをうまく活用するために必要なのは、「任せきり」ではなく「一緒に作る」意識です。
ルールを整備し、情報を共有し、改善しながら進めることで、
物流は“ただの作業”から、“ブランドの信頼を支える力”へと進化します。
こうした取り組みを続けることで、アウトソーシングは単なる「業務委託」ではなく、
ビジネスを共に育てるためのパートナー戦略として、真価を発揮するようになります。
◾️神谷商店の物流アウトソーシングでできること・強み
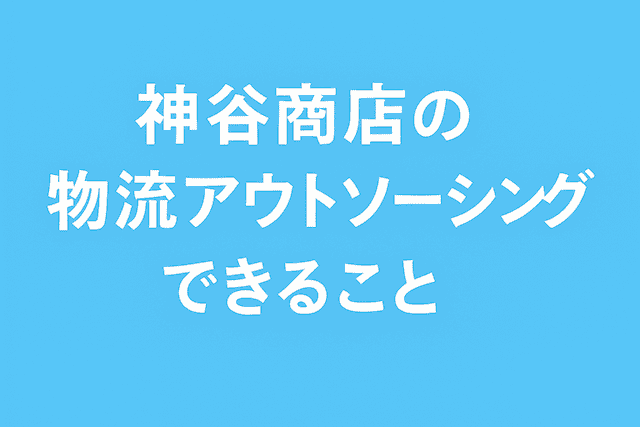
物流アウトソーシングを検討する際、「どこに頼むか」はとても大切なポイントです。
私たち神谷商店は、長年の現場経験と柔軟な対応力を活かし、
お客様の事業フェーズや悩みに寄り添った物流支援を行っています。
ここでは、神谷商店が提供できる具体的なサポートと、他社にはない強みをご紹介します。
小規模からでもスタートできる柔軟な体制
私たちの物流支援は、「月に数十件」からのスタートも大歓迎。
最初は小ロット、徐々に件数が増えてもそのままスムーズに対応可能です。
スモールスタートから成長まで、一貫して支えるのが私たちの役割です。
幅広い対応力と個別カスタマイズ
出荷作業にとどまらず、
- 販促物の同梱
- ギフトラッピング・熨斗(のし)対応
- 返品商品の再検品・再商品化
といった細かなご要望にも一社一社ごとに柔軟にカスタマイズ対応しています。
「こんなことも頼める?」というご相談、大歓迎です。
現場主導の検品・出荷オペレーション
神谷商店では、物流現場で実際に手を動かすスタッフが中心となって運用改善を重ねています。
机上のシステム設計だけでなく、“現場で本当に使いやすい”仕組みを追求。
これにより、出荷ミスの低減・在庫ズレの解消など、数多くのECショップ様から信頼をいただいています。
顧客満足を高める梱包品質
「届いたときの印象」までがネットショップの品質だと、私たちは考えます。
そのため、丁寧で整った梱包、商品に合わせた緩衝材の選定、スピーディーな出荷を徹底しています。
レビューやリピートにつながる、そんな“目に見えない価値”を物流からつくっていきます。
柔軟性と相談しやすさが強み
そして何よりの強みは、「小回りがきく」「気軽に相談できる」こと。
- キャンペーンにあわせた特別対応
- 急な商品変更や納品の遅れ
- 月ごとの出荷数のばらつき
こうした“予定外”にも柔軟に対応できるのが、中小物流事業者としての神谷商店の魅力です。
システムでは解決できない、人の対応力が私たちの誇りです。
♦︎神谷商店は、成長に寄り添う物流パートナー
物流アウトソーシングは、「任せて終わり」ではなく、「一緒に育てていくパートナーシップ」です。
神谷商店は、ただ荷物を出すだけでなく、お客様と一緒に課題を見つけ、改善し、成長を支えることを目指しています。
ネットショップの立ち上げから、拡大フェーズ、繁忙期の対応まで、
どんな場面でも“ちょうどいい物流”を、あなたの隣で支えます。
まとめ:物流アウトソーシングはビジネス成長の土台に
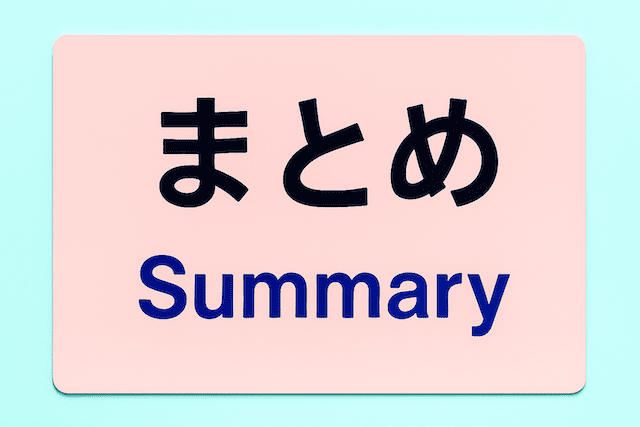
ネットショップや小売ビジネスを運営していく中で、
「商品を売る」ことと同じくらい大切なのが、「商品を正しく、早く、お客様に届けること」です。
その重要な役割を担うのが、物流アウトソーシングです。
出荷作業や在庫管理といった業務を外部に委託することで、
本来自分たちがやるべき商品開発や販売戦略に集中できるようになります。
ミスも減り、お客様の満足度も向上し、レビュー評価やリピート購入にも好影響が生まれます。
とくに、注文が増えてきたタイミング、
人手が足りずに日々バタバタしている状況、
これから大きく事業を伸ばしていきたいと考えているフェーズ――
そんなときに、物流のプロと一緒に仕組みを整えることは、未来への安心と成長のための土台づくりになります。
そして、神谷商店のような柔軟で相談しやすい物流パートナーがいれば、
“倉庫”ではなく“チームの一員”として、あなたのビジネスを支えてくれる存在になれるはずです。
アウトソーシングは、ただの外注ではなく、「一緒に走ってくれる力」――。
あなたのブランドがもっと強く、もっと遠くへ届くために、物流から支えていきます。
↓↓お問い合わせはこちら↓↓










