ロット数とは?物流現場での意味と管理の重要性をわかりやすく解説

ロット数ってなに?かんたんに解説します
ロット数の数え方や扱いの注意点
ロット数が多いと何が大変?物流現場のリアル
神谷商店の「ロット対応力」とは?
まとめ:ロット管理の不安、まずはご相談ください

ロット数ってなに?かんたんに解説します

物流現場や製造業の会話の中で、当たり前のように登場する「ロット」や「ロット数」という言葉。しかし、初めて業界に入った方や、物流部門以外の方には、少し分かりにくいかもしれません。
ここでは、ロットの基本的な意味や考え方、ロット数との違い、実際の使われ方まで、初心者の方でも理解できるようにかんたんに解説します。
ロットとは?ー「製造・仕入れのくくり」のこと
「ロット(lot)」とは、ある条件下で一括して製造・仕入れ・加工された商品の単位を指す言葉です。
たとえば、工場で1日に1,000個のドリンクを製造したとします。この1,000個は、同じライン・同じ日時・同じ原材料で作られており、品質や内容が同じであるため、「1ロット」として扱います。
ロットの具体例:
- 医薬品:1回の製造工程で製造された錠剤 → ロット番号「P20240901」
- 食品:2025年6月10日に焼いたクッキー100箱 → ロット番号「B0610」
- 日用品:海外からの輸入品で、1便に乗っていた雑貨類 → 輸入ロット「L2025HK07」
このように、「ロット」は“ひとまとめ”を意味し、商品に割り振られる「ロット番号」によって、いつ・どこで・どんな条件で作られたものかを追跡できるように管理されています。
ロット番号の役割とは?
ロット番号は、製造日・仕入れ日・製造ラインなどに基づいて付けられる管理用の識別記号です。
この番号があることで、商品の品質管理や出荷履歴の確認がスムーズに行えるようになります。
たとえば、ある商品にトラブルが発生した場合、「どのロットから発生した不良なのか?」を確認することで、対象商品だけをピックアップして対応できます。
逆に言えば、ロット番号が無いと、全数調査が必要になるなど、大きな手間・コスト・信用問題に発展してしまうリスクが高まります。
ロット「数」って何?
「ロット数」とは、同じ商品に存在する異なるロットの“種類の数”のことです。
例:
商品Aの在庫が以下のような内訳だったとします。
| ロット番号 | 在庫数 |
| L20240601 | 100個 |
| L20240610 | 200個 |
| L20240615 | 150個 |
この場合、商品Aのロット数は「3」ということになります。
つまり、ロット数は数量のことではなく、“管理すべきグループ数”というイメージでとらえると分かりやすいでしょう。
ロットと「商品数」の違いに注意!
ここで気をつけたいのが、「ロット数=在庫数」ではない、という点です。
- 商品数:在庫の合計数量(例:100個+200個+150個=450個)
- ロット数:ロットの種類数(例:3ロット)
ロットが異なると、それぞれの品質保証や出荷条件も異なることがあるため、同じ商品でも「別物」として扱う必要があります。
ロットはなぜこんなに使われるのか?
ロット管理が行われている業界は非常に多くあります。
特に、以下のような業種では必須の管理項目といえるでしょう。
- 食品業界(賞味期限・製造日管理)
- 医薬品業界(製造記録・品質保証)
- 化粧品・日用品(成分管理・製造証明)
- 自動車・電気機器(部品のトレーサビリティ)
このような業界では、商品そのものの品質管理=企業の信頼そのものに直結します。
まとめ:ロットは“信頼の履歴書”
ロットとは、ただの番号ではありません。
「この商品は、いつ・どこで・どのように作られたか」を示す、いわば“商品の履歴書”のような存在です。
ロット数が多くなると管理の負担は増しますが、
その分だけ「品質を守り、責任を果たす」ための手段ともいえます。
なぜロット数の管理が重要なの?

ロット数を把握し、正しく管理することは、単なる在庫の把握にとどまりません。
むしろ、品質保証・トレーサビリティ・リスク回避など、物流や製造業の信頼を支える「基盤」となる重要な業務です。
ここでは、ロット管理がなぜ重要なのか、主に3つの観点から解説します。
1. 不良品発生時のトレーサビリティ(追跡性)
ロット管理の最大の目的の一つが、「不良発生時に、該当商品を追跡できること」です。
たとえば、出荷した商品に不良があった場合:
- ロット番号があれば:どの生産ロットか特定でき、そのロット分だけを回収・調査
- ロット番号がない場合:すべての在庫や出荷分を対象に確認・回収する必要がある
この違いは、対応のスピード・コスト・信頼性に直結します。
とくに食品・医薬品・化粧品などの分野では、法令でトレーサビリティの確保が求められることもあるほど、重要な管理項目なのです。
2. 賞味期限・使用期限など「期限管理」に必須
食品や薬品、日用品などでは、「どれがいつまで使える商品なのか?」を正確に把握する必要があります。
このとき、ロット番号と一緒に管理することで、期限が近いものから優先して出荷する(先入れ先出し:FIFO)という運用が可能になります。
ロット管理があると:
- 古い在庫から優先して出荷し、廃棄ロスを最小限に抑える
- 期限切れ商品が倉庫内に混在するリスクを低減
- 出荷時に「このロットは〇〇まで使用可能」と明確に確認できる
特に温度管理が必要な商材や衛生商品では、ロットごとの有効期限の把握が品質維持に不可欠です。
3. 証明書や検査記録と連動し、信頼性を担保できる
BtoB取引やメーカー系の現場では、出荷時に「製品の品質証明書」「検査成績書」などを提出することがあります。
このような書類は、ロット番号単位で発行・保管されるのが一般的で、
「この商品は、どの試験をクリアしたロットか?」
「このロットの製品は、どの製造記録に紐づいているか?」
といった情報が正しく管理されていないと、提出漏れや証明不能による信頼低下につながります。
ロット管理ができていないとどうなる?
逆に、ロット番号が曖昧だったり、記録に不備があった場合には、以下のような問題が起こりやすくなります:
| 問題の例 | 結果 |
| 不良の発生ロットが特定できない | 対象外商品まで回収・損失拡大 |
| 期限切れ商品が誤出荷 | クレーム・法令違反のリスク |
| 証明書の提出ができない | 取引停止や信用低下の可能性 |
| 出荷実績とロット履歴が不一致 | 在庫精度低下・WMSの信頼性崩壊 |
まとめ:ロット管理は「企業の信頼そのもの」
ロット数の管理は、ただの数字合わせではありません。
それは、「品質を保証し、責任を持って出荷する体制があるか?」という企業の信頼の証でもあります。
特にBtoBでの取引が多い企業ほど、ロット管理の体制があるかどうかで、取引の継続や新規受注の可能性が左右されることも珍しくありません。
ロット数が多いと何が大変?物流現場のリアル

ロット数の管理は、企業の信頼や品質保証にとって重要な役割を果たしますが、一方でロット数が増えると物流現場では大きな負担が発生します。
ここでは、現場で起こりがちなトラブルや管理上の苦労を、リアルな視点から紹介します。
1. ピッキングミスのリスクが上がる
同じ商品でも、ロット番号が異なれば「別商品」として管理・出荷する必要があります。
しかし、現場では:
- 商品の外観が全く同じ
- ロット番号の桁や表記が似ている
- 棚の中で複数ロットが混在している
といったケースが多く、ロット指定出荷におけるピッキングミスが起こりやすくなります。
特に以下のような状況では要注意です:
- LOT202309 と LOT202309A のような似た番号の混在
- 「最新ロットで出荷して」と言われたが判断が曖昧
- 先入れ先出しの指示が現場に正しく伝わっていない
ミスが起きれば、出荷後の回収・再配送対応など、コストと信頼の両方にダメージを受けかねません。
2. 保管棚が圧迫される
ロット数が多いと、それだけ保管スペースの確保も必要になります。
同じSKU(品番)でもロットが異なれば、混載せずに区分保管する必要があるため:
- 棚1つに1ロットしか置けない
- 小ロットがたくさん並び、無駄なスペースが生まれる
- ロケーションが分散し、探す手間が増える
といった問題が発生しやすくなります。
さらに、保管棚が足りない場合は仮置き・重ね置きになりやすく、誤出荷や破損リスクが高まるため、管理者としてもヒヤヒヤする場面が増えるのが現実です。
3. 棚卸しや在庫照合が複雑になる
ロット数が増えると、棚卸しの難易度も跳ね上がります。
在庫数だけでなく、「どのロットが、いくつ残っているか」までチェックする必要があるため:
- 現物のラベルが薄れて見えない
- ロットが混在していて区分が不明
- システム上は存在するが現物がない(ロケーションミス)
といった「在庫精度のズレ」が起こりやすくなります。
また、ロットを記録する必要がある分、作業スピードも遅くなり、作業負荷が跳ね上がるのも現場のリアルな悩みです。
4. システム入力・伝票発行の手間が増える
ロット単位での出荷になると、伝票やシステム入力にもロット番号が必要になる場合が多くあります。
- 出荷ラベルにロット番号を明記
- WMS上でロット選択・数量入力が必要
- 納品書や請求書へのロット記載対応
このような事務的作業が発生し、少量出荷でも“作業ステップ”が増えることで、ミスや時間ロスにつながりやすくなります。
現場でよくある悩みまとめ
| 課題 | 内容 | 発生しやすい問題 |
| ピッキングミス | ロット違いの誤出荷 | クレーム・返品・再配送料 |
| 保管棚の圧迫 | ロットごとに分ける必要あり | スペース不足・保管効率低下 |
| 棚卸し負担増 | 数量+ロットを照合 | 在庫ズレ・工数増大 |
| 情報入力の手間 | ロット番号の記録・伝票反映 | 入力ミス・作業遅延 |
まとめ:ロット管理は「見えない手間」が多い
ロット数が増えるということは、それだけ見えない作業・管理の工数が増えるということです。
- 品質は守りたいけど、管理が追いつかない
- 指定ロットの出荷に毎回時間がかかる
- そもそも誰もロットの扱いを教えてくれていない
――そんな悩みを感じたら、一度「ロット管理の仕組み自体」を見直すことも大切です。
神谷商店の「ロット対応力」とは?

ロット数が多くなるほど、出荷・保管・棚卸しといった物流業務は複雑になります。
その中でも神谷商店は、現場での混乱やミスを最小限に抑える“運用設計”と“仕組み”に強みを持っています。
1. ロット別のロケーション管理で「探さない倉庫」運用
当社では、ロット番号ごとに保管ロケーションを明確に区分け。
似たようなロットが混在しても、「どのロットがどこにあるか」が即座に把握できる体制を整えています。
- ロット混在を防ぐ棚配置
- ロットごとの定位置ルール
- ラベル・表示の見やすさを工夫
これにより、ピッキング時の探し回りや誤出荷を大幅に減少させることができています。
2. WMSでロット単位のトレーサビリティを徹底
神谷商店ではWMS(倉庫管理システム)を活用し、
「いつ・どこから・どこへ・どのロットが動いたか」という情報をリアルタイムで記録・追跡。
- 出庫/入庫履歴をロット単位で自動記録
- 指定ロットでの出荷指示もシステムで正確に対応
- 在庫照合や棚卸しもロット単位でスムーズに
手書きや目視による確認に頼らず、システムで管理を標準化していることが、ミスの発生を抑えるポイントです。
3. 物量に応じてロット数の増減にも柔軟対応
繁忙期やスポット案件などで、ロット数が急増するケースでも対応可能な体制を整えています。
- 一時的に増えるロット用の「臨時ロケーション」確保
- シフト配置をロット数に合わせて調整
- 作業指示書にもロット別の明示を徹底
物量・ロットの変動があっても、現場が混乱しない仕組み作りを重視しています。
「ロットが多くても、作業が止まらない」
それが神谷商店のロット対応体制です。
「たくさんのロットがあるから仕方ない」ではなく、
「ロットが多くても、正確に・スムーズに回す」ことを前提とした現場設計・人員教育・仕組みづくりを行っているからこそ、
ヒューマンエラーや在庫不一致といった“物流事故”を限りなく減らすことができています。
まとめ:ロット管理の不安、まずはご相談ください
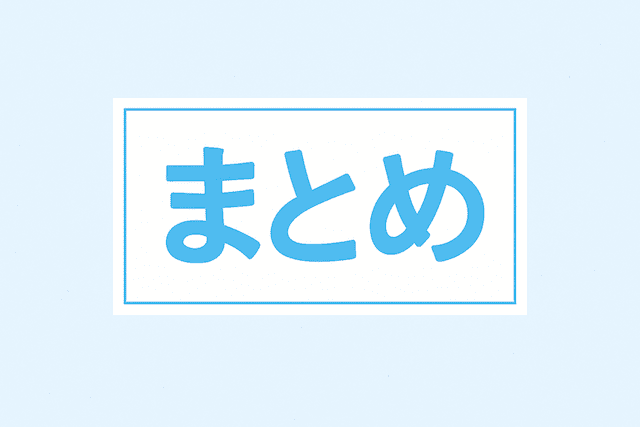
ロット管理は、ただ「在庫を数える」だけの作業ではありません。
トレーサビリティの確保、品質の保証、誤出荷防止、在庫精度の維持といった、
物流全体の信頼性を左右する重要な業務です。
とくにロット数が多い現場では、
- 出荷時のピッキングミス
- 保管ロケーションの混乱
- 棚卸しや在庫照合の負担増
- トラブル発生時の追跡不能
といったリスクが高まりやすくなります。
神谷商店では、これらの課題に対して
- ロット単位のロケーション管理
- WMSによるリアルタイムなトレーサビリティ
- 作業手順・体制の仕組み化
といった“ミスが起きにくい物流環境”を整備し、お客様の商品を正確かつ丁寧に取り扱うことを徹底しています。
「ロットが多いと面倒」「毎回ロットを意識して作業するのが大変」
そんなお悩みの裏側には、“仕組み”と“設計”の問題があるかもしれません。
「ロット管理に強い倉庫」という視点で、神谷商店の物流品質をぜひ一度ご覧いただければ幸いです。










